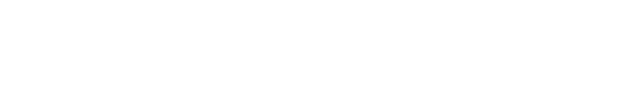音響外傷(ヘッドホン難聴)
音響外傷(ヘッドホン難聴)とは?
スマートフォンや音楽配信サービスの普及により、イヤホンやヘッドホンを長時間使用する若年層が増えています。その結果、「音響外傷」や「ヘッドホン難聴」といった聴覚障害のリスクが高まっています。
音響外傷とは?
内耳への物理的ダメージ
音響外傷とは、強大な音刺激による内耳の障害です。蝸牛内の繊毛細胞が大音量によって傷つき、難聴や耳鳴りなどの聴覚障害を引き起こします。一度損傷した繊毛細胞は、ほとんど再生しません。
昔と今で異なる発症原因
かつては工場・建設現場などでの騒音性難聴が中心でしたが、現在ではイヤホンやヘッドホンの長時間使用による「ヘッドホン難聴」が増加しています。特に若年性難聴として問題視されています。
音響外傷の主な症状
- 難聴(特に高音域)
- 耳鳴り(「キーン」「ジー」)
- 音の歪み
- 耳の閉塞感
- 小さな音にも過敏になる(聴覚過敏も稀だが起こりうる)
ヘッドホン難聴の実態とリスク
若年層に広がる背景
当院のアンケートによると、中高生の約70%が「毎日1時間以上イヤホン使用」、そのうち30%は「音量を最大の70%以上」に設定していました。
WHOも10億人以上の若者が難聴リスクにあると警告しています。
イヤホンの種類と影響の違い
- カナル型イヤホン:音源が内耳に近くリスクが高い
- オーバーイヤー型イヤホン:音量を上げにくいが密閉性が高い
- 骨伝導型ヘッドホン:鼓膜にはやさしいが内耳への音圧伝達は回避できないため大音量はリスク
生活音のデシベルと安全な聴取時間
- 図書館:30-40dB
- 通常の会話:60dB
- 電車:80dB
- イヤホン最大音量:100〜110dB
100dBを超える音は数分の暴露でも聴力に影響を及ぼす可能性があります。
音響外傷になりやすい人の特徴
- 毎日2時間以上イヤホン・ヘッドホンを使う人
- 音量を最大の60%以上にしている人
- 騒音環境で使用する(電車内など)
- 中耳炎など耳の病気の既往歴がある人
- 喫煙者(内耳の血流低下)
- 騒音の多い職場に勤務
- 音楽ライブやクラブによく行く
- 40歳以上の方
音響外傷の治療法
薬物療法
- ステロイド剤:炎症を抑制
- 血流改善薬:内耳の循環改善
- ビタミン剤:代謝促進
安静と聴覚の休養
少なくとも1~2週間は静かな環境で耳を休めることが必要です。
補聴器の使用
聴力が戻らない場合には補聴器での補助を検討します。
音響外傷の予防法
60-60ルールの実践
- 音量は最大の60%以下
- 連続使用は60分以内
ノイズキャンセリング機能を活用
周囲の騒音を遮断することで音量を上げずに済みます。
音量制限アプリの利用
スマートフォンにある音量制限機能やアプリの使用を推奨します。
早期の受診
若年性難聴は気づきにくいため、少しでも違和感があれば早期受診が必要です。
正しいイヤホン・ヘッドホンの使い方
- 人と会話できる音量が適切
- 1時間使用したら10分休む
- 両耳ではなく片耳ずつ交互に使用
- オープン型イヤホンの選択
- 寝ながらの使用は避ける
最近のスマホには「ヘルスケア機能」があり、使用時間や音量を記録し警告してくれます。積極的に活用しましょう。
よくある質問(FAQ)
Q. 音響外傷とはどんな病気?
一般に、大型ライブやイヤホン大音量などで内耳有毛細胞が破壊され、高音域難聴・耳鳴り・音のゆがみが急に表れ、不可逆的に残存しうる耳の外傷性障害を「音響外傷」と呼びます。
Q. どんな症状が出たら受診すべき?
ライブ翌朝や長時間イヤホン後に高音の聞こえ低下やキーンという耳鳴り、耳閉感が数時間続く場合は、時間との勝負で治療効果が変わるため必ず当日中に早急に受診してください。
Q. 具体的な治療内容は?
急性期には内耳の炎症と浮腫を抑えるステロイドを主軸に循環改善薬とビタミン剤を併用します。効果を最大化するため発症後48時間以内の開始が理想です。
Q. ステロイドはいつまでに始める?
ステロイドは発症から48時間以内、遅くとも1週間以内に開始すると聴力改善率が大幅に上昇します。それ以降でも一定の効果は期待できますが回復度は低下するため、早期受診が重要です。
Q. 治療後に聴力は戻る?
聴力は軽症なら数日で回復する例もありますが、重症例や受診遅延では完全に戻らず高音域に後遺症が残ることが多く、補聴器を要する場合もあります。個人差は大きいため早期治療が最重要です。
Q. ノイズキャンセルは効果的?
ノイズキャンセル機能は外部騒音を減らし、音量を下げてもクリアに聞こえるため難聴予防に有効です。ただし音量を上げすぎれば同じリスクがあるので設定は60%以下を徹底してください。
まとめ
私たちの耳は、一度失った聴力を回復させることが困難です。音楽を楽しみながらも、正しい使い方で聴覚を守ることは十分に可能です。若いうちから耳を大切にする習慣を持ち、将来にわたって良好な聴力を維持していきましょう。
参考文献
- 日本耳鼻咽喉科学会編. (2023). 『耳鼻咽喉科診療ガイドライン』. 金原出版.
- (2022). "World report on hearing". World Health Organization.
- 喜田村健, 森満保. (2023). 『臨床耳鼻咽喉科学』. 中山書店.
- 河野淳. (2022). 『音響外傷と騒音性難聴』. 医学書院.
- Kujawa SG, Liberman MC. (2021). "Adding insult to injury..." Journal of Neuroscience.
- 日本聴覚医学会編. (2023). 『スマートフォン時代の聴覚障害』. 金原出版.
- Le Prell CG, et al. (2022). Ear and Hearing.
- 内田育恵, 植田広海. (2023). Audiology Japan.