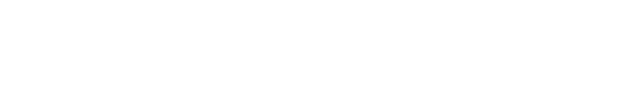メニエール病
メニエール病の原因
メニエール病の発症メカニズムとして広く受け入れられているのが「内リンパ水腫説」です。
内耳には、平衡感覚と聴覚をつかさどる器官(蝸牛・前庭・三半規管など)があり、それぞれの器官はリンパ液(内リンパと外リンパ)で満たされています。
何らかの原因で内リンパ液が過剰に貯留(内リンパ水腫)し、内耳の中の圧力バランスが崩れると、聴覚や平衡感覚に障害が生じます。この内リンパ水腫が慢性的に起こることで、メニエール病のめまいや難聴が引き起こされると考えられています。
メニエール病の症状|めまい・耳鳴り・耳閉感・難聴の特徴
メニエール病の症状は主に以下の4つです
めまい発作
突然の激しい回転性めまいが数十分〜数時間続きます。
吐き気や嘔吐を伴うこともあり、発作時は立っていられないほどです。
耳鳴り
キーン、ジー、ブーンといった持続音が片側の耳に生じます。
めまい発作と同時に強くなり、発作後に軽減する場合もあります。
難聴
発作とともに聴力が低下します。初期は低音域の難聴が目立ちますが、病気が進行すると全体的に聴力が落ちることもあります。
耳閉感
耳が詰まったような圧迫感を感じます。飛行機で耳が塞がった時のような不快感が続くのが特徴です。症状は発作的に現れ、しばらくすると自然に軽快することもありますが、何度も繰り返すことで症状が残るようになることもあります。
メニエール病の経過と治り方|再発・後遺症の可能性は?
メニエール病の発作は数週間〜数ヶ月おきに繰り返されることが多く、初期には症状が完全に回復することもあります。しかし、再発を繰り返すうちに聴力が回復しにくくなり、最終的には慢性的な感音難聴が残ることもあります。
また、長期的には発作の頻度が徐々に減少していく傾向がありますが、突然再発するケースもあるため、慢性疾患としての継続的な管理が重要です。
メニエール病の診断方法と検査内容
メニエール病の診断は、以下のような検査と問診に基づいて総合的に行われます。
問診・症状の聴取
めまいの回数・持続時間・耳鳴りや難聴との関係などが重要です。
聴力検査
初期には低音域の感音難聴が特徴的ですが、進行すると高音域にも影響が出ます。
平衡機能検査(眼振検査)
三半規管などの前庭機能の異常を確認します。
内耳MRI
必要に応じて腫瘍などの器質的疾患(前庭神経鞘腫など)との鑑別目的で行います。
(当院では施行しておりません。)
メニエール病と間違えやすい他の病気との違い
メニエール病と似た症状を呈する疾患には、以下のようなものがあります。
良性発作性頭位めまい症(BPPV)
特定の頭の動きに応じて回転性めまいが起こります。持続は数十秒程度と短いです。通常、難聴や耳鳴りは伴いません。
突発性難聴
明らかな原因もなく突然の片側の耳の聞こえが悪くなる原因不明の感音難聴です。また、耳鳴りやめまいを伴うことも多いです。通常は1度しか起こらず繰り返しにくいのが特徴です。
前庭神経炎
突然の強い回転性めまいと吐き気を生じます。安静にしてもめまい症状が改善しないことが多いです。症状は数日間持続しますが、難聴や耳鳴りなど聴覚症状は伴いません。
自律神経失調症や不安障害
日常生活の強いストレスにより自律神経のバランスが崩れて平衡感覚の不安定さや倦怠感、吐き気などの様々な症状を引き起こします。回転性めまいは少ないです。
これらとの鑑別には、専門的な診察と検査が不可欠です。
メニエール病の治療法|薬物療法・生活指導・手術の選択肢
メニエール病の治療は、症状のコントロールと再発予防が中心になります。
保存的治療(薬物治療)
利尿剤
内リンパ水腫の改善を目的に使用されます。
抗めまい薬
めまい発作を抑制するために使用。
ビタミンB群・循環改善薬
内耳の血流改善を目的とした補助療法。
抗不安薬・睡眠導入薬
ストレスや不眠がめまいを悪化させることがあるため、必要に応じて使用します。
発作時の対症療法
鎮吐薬や安静、点滴治療で症状を軽減します。
生活指導・セルフケア
- 塩分制限(1日6g未満を推奨)
- 十分な睡眠と規則正しい生活
- 水分をこまめに摂る
- 禁煙
- 有酸素運動
難治例に対する治療
鼓室内ステロイド注入療法
局所的に炎症を抑える治療。(当院では施行しておりません)
外科的治療(内リンパ嚢開放術、前庭神経切断術など)
重症例や薬剤抵抗例に検討されます。(当院では施行しておりません)
受診の目安 ― こんなときは耳鼻科へ
| 目安 | 解説 |
|---|---|
| 発作が月 1 回以上 | 繰り返すほど聴力低下が固定化しやすいため、治療強化を検討します。 |
| 片側だけだった症状が両耳に波及 | 両側化の兆候です。難聴が残存しやすいので早期受診が推奨されます。 |
|
発作が12 時間超 または回転性めまい発作が 1日に2回以上 |
"典型"を超える経過は鑑別が必須となります。 |
メニエール病と付き合う生活での工夫・セルフケア方法
メニエール病は「発作さえなければ普通の生活が送れる病気」です。
日々の生活管理によって発作頻度を減らし、症状の進行を防ぐことが可能です。
- 疲労・睡眠不足を避ける
- 音の刺激(大音量の音楽、工事音など)を控える
- 気圧変化(飛行機・登山など)にも注意
- 記録をつけて発作のパターンを把握
まとめ
メニエール病は、回転性めまいや耳鳴り・難聴を繰り返す内耳の病気です。
内リンパ水腫が原因とされ、生活の質を大きく損なうことがありますが、適切な診断と治療、生活管理によってコントロール可能です。繰り返すめまいや聴力低下を感じた場合は、早めに耳鼻科専門医の診察を受けましょう。
よくある質問
メニエール病の発作時、救急車を呼ぶべきタイミングは?
意識障害や強い嘔吐、転倒など危険が伴う場合は救急要請を検討してください。
子どもや若い人でもメニエール病になりますか?
主に30~50代に多いですが、まれに若年層でも発症することがあります。
両耳に症状が出ることもありますか?
初期は片耳のみが多く、経過により両耳に及ぶこともあります。
メニエール病はストレスで悪化しますか?
はい。ストレスや疲労は発作の引き金になりやすく、生活習慣の見直しが重要です。
飛行機や高所で悪化することはありますか?
気圧変化で耳に負担がかかると症状が出やすくなる場合があります。対策が必要です。
仕事は続けられますか?
高所作業や重機操作など危険を伴う業務は配置転換が望ましいケースもあります。専門医にご相談ください。
参考文献
- 日本めまい平衡医学会. めまい・平衡障害診療ガイドライン 2022. 南江堂, 2022.
- 日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会. メニエール病診療ガイドライン2017. 金原出版.
- Watanabe Y, Mizukoshi K, Shojaku H, et al. "Meniere's disease." Orphanet J Rare Dis. 2010; 5:12.
- Gurkov R, Pyyk? I, Zou J, Kentala E. "What is Meniere's disease? A contemporary re-evaluation of endolymphatic hydrops." J Neurol. 2016; 263 Suppl 1(Suppl 1):S71-S81.
- Nakashima T, Pyykk? I, Arroll MA, et al. "Meniere's disease." Nat Rev Dis Primers. 2016; 2:16028.