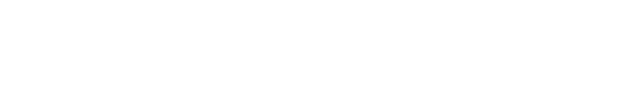インフルエンザ
インフルエンザは毎年冬に流行し、強い倦怠感や関節痛など風邪とは違う重い症状を引き起こします。特に小児・高齢者・基礎疾患のある方は肺炎や脳症など重症化のリスクが高いため要注意です。
インフルエンザの原因と感染経路|A型・B型ウイルスの特徴
インフルエンザは、インフルエンザウイルスによって引き起こされる感染症で、主にA型・B型・C型の3種類があります。
なかでも毎年流行するのはA型とB型で、A型は特に変異しやすく、大流行(パンデミック)の原因となることがあります。
感染経路は主に以下の2つです。
- 飛沫感染:咳やくしゃみによって放出されたウイルスを含む飛沫を吸い込む
- 接触感染:ウイルスが付着した手指や物に触れ、口や鼻から体内に入る
インフルエンザの潜伏期間は通常1~3日(最長4日)で、発症の1日前からウイルスを排出し始めるため、気づかないうちに周囲に感染を広げてしまうこともあります。
インフルエンザの主な症状と風邪との違い
インフルエンザと一般的な風邪は似たような症状もありますが、以下のように違いがあります。
| 症状 | インフルエンザ | 一般的な風邪 |
|---|---|---|
| 発熱 | 急に38~40℃の高熱 | ゆるやかな発熱、微熱程度 |
| 倦怠感 | 強い全身のだるさ | 軽度の疲労感 |
| 関節・筋肉痛 | よくみられる | ほとんどなし |
| 咳・鼻水 | 2~3日後から強くなる | 初期からみられる |
| 回復まで | 1週間前後 | 数日で軽快することが多い |
また、乳幼児ではけいれんや嘔吐、高齢者では肺炎のリスクが高くなるなど、年代によって注意すべき症状も異なります。
インフルエンザの検査方法|迅速診断とその精度
インフルエンザの検査として迅速抗原検査が主流です。
鼻咽頭から検体を採取し、15~30分程度で結果が出るため、発症早期でも感染の有無を判断することが可能です。なお、検査の精度は発症から12時間以上経過してからの方が陽性率が高いとされており、タイミングを見極めることも大切です。
重症化リスクの高い方(高齢者・小児・妊婦・基礎疾患のある方)には、より早い診断・治療開始が推奨されます。
インフルエンザの治療薬の種類と選び方
インフルエンザに対しては、ウイルスの増殖を抑える抗ウイルス薬が有効です。
主な薬剤と特徴
| 薬剤名 | 投与方法 | 特徴 |
|---|---|---|
| タミフル(オセルタミビル) | 内服(1日2回×5日) | 小児・高齢者にも対応。予防投与にも使用可能 |
| ゾフルーザ(バロキサビル) | 内服(1回) | 1回の服用で完了。10歳以上対象 |
| イナビル | 吸入(1回) | 吸入可能な5歳以上は使用可。吸入が苦手な方には不向き |
| ラピアクタ | 点滴 | 重症例や内服困難な方に使用 (当院では取り扱っておりません。) |
発症から48時間以内に投与を開始することで、症状の軽減・回復の早期化・周囲への感染拡大防止につながります。
異常行動は一過性で多くは軽快しますが、小児は投与後2日は見守りが推奨されています。
インフルエンザのワクチン接種
インフルエンザを予防するうえで最も有効な方法はワクチン接種です。
インフルエンザワクチンの特徴
- 毎年流行するウイルスの型に合わせて製造
- 接種から2週間程度で効果が発現
- 効果の持続は約5ヶ月
- 重症化の予防効果が高い
特に以下の方には積極的な接種をおすすめします:
- 65歳以上の高齢者
- 小児(特に6ヶ月~小学生)
- 基礎疾患をお持ちの方(喘息・心疾患など)
- 医療・介護従事者
- 妊婦の方
自宅でのインフルエンザ対処法と注意点
発症後は安静と水分補給が基本です。食欲がなくても水分はしっかりと摂るようにしましょう。
また、以下のような行動を心がけましょう。
- 解熱後も2日間は自宅療養を(ウイルス排出が続くため)
- 咳エチケットと手洗いを徹底
- 無理な外出は控える(登園・登校・出勤停止の目安あり)
- 部屋の湿度を50~60%に保つ(ウイルスの活性を抑える効果あり)
症状が軽快しても油断せず、再発熱や呼吸困難、意識障害などがあればすぐ医療機関の受診が必要です。
ご不安な症状やご相談があれば、どうぞお気軽にご相談ください。
まとめ
インフルエンザは高熱・強い倦怠感が特徴で、小児・高齢者では重症化のリスクが高まります。発症後48 時間以内の抗ウイルス薬投与と毎年のワクチン接種が重症化防止の鍵となります。
Q. 登園・登校はいつから再開できますか?
発症後5日を経過し、かつ解熱後2日以上たってからが登園・登校の目安です。
Q. ワクチンを接種しても感染するのはなぜ?
ウイルスの型が一致しない場合や免疫が十分でない場合、感染することがあります。
Q. インフルエンザとコロナの見分け方はありますか?
症状だけでは判別困難です。正確な診断には検査が必要ですので受診をおすすめします。
Q. 家族に感染者が出た場合、他の家族はどうすれば?
手洗い・換気・マスク着用を徹底し、必要に応じて予防投薬を検討します。
Q. 妊娠中や授乳中にかかった場合、どうすれば?
妊婦や授乳中の方も使用できる薬があります。必ず医師に相談してください。
Q. 薬を飲まずに自然に治すことはできますか?
若く健康な方は自然回復もありますが、重症化リスクや周囲への感染拡大に注意が必要です。
Q. なぜ毎年ワクチンを打たなければならないの?
ウイルスが毎年変異するため、流行株に合わせたワクチン接種が必要です。
Q. インフルエンザは1シーズンに2回かかることもありますか?
A型とB型の両方に感染することもあり、1シーズンに2回かかる可能性もあります。
Q. 学校や職場で流行時にできる予防策は?
マスク着用・手洗い・こまめな換気・人混みの回避が効果的です。
Q. タミフルなどの副作用は心配ありませんか?
一部に異常行動などの報告がありますが、多くは一時的で安全性は確立されています。
Q. インフルエンザの感染力は?
発症1日前から感染力があり、特に最初の3日間が最も感染性が高いです。
参考文献
- 日本感染症学会「インフルエンザ診療ガイドライン2023」
- 厚生労働省「令和6年度インフルエンザQ&A」
- 厚生労働省 資料「季節性インフルエンザHAワクチン推奨株に関する方針」2024 年6 月
- 国立感染症研究所 IASR 492 号:インフルエンザ潜伏期間等
- 塩野義製薬/医療情報サイト「ゾフルーザ概要」2024 年更新