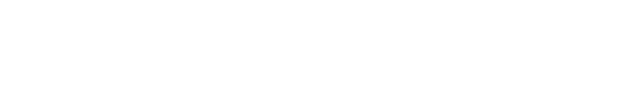滲出性中耳炎
滲出性中耳炎とは
滲出性中耳炎(OME:Otitis Media with Effusion)は、中耳に滲出液(耳だまりの液体)が溜まる病気です。
急性中耳炎と異なり、痛みや発熱を伴わないことが多いため、気づきにくく発見が遅れることもあります。
中耳の役割と構造
耳は「外耳」「中耳」「内耳」の3つの部分に分かれており、中耳は鼓膜の奥にあります。
中耳は耳管(じかん)という細い管を通じて鼻の奥とつながっており、ここを通して換気や圧力調整が行われます。
なぜ液体が溜まるのか?
風邪やアレルギー、アデノイドの肥大などによって耳管の働きが低下すると、十分な換気が行えず中耳内に液体がたまり、滲出性中耳炎が発生します。
滲出性中耳炎の原因
風邪や上気道炎
風邪によって耳管が腫れて詰まり、中耳の換気が悪くなることで発症します。
アレルギー性鼻炎
アレルギーによる粘膜の腫れが耳管の機能を低下させ、液体の滞留を招きます。
アデノイド肥大
アデノイド(鼻の奥にあるリンパ組織)が大きくなると耳管を圧迫し、滲出性中耳炎の原因となります。
耳管の未発達(子どもの特徴)
子どもの耳管は大人に比べて短く水平であるため、ウイルスや細菌が入りやすく、液体がたまりやすい傾向があります。
滲出性中耳炎の主な症状
- 耳が詰まった感じ(耳閉感)
- 難聴(聞こえづらさ)
- 自分の声が響く(こもる感じ)
- 集中力の低下
子どもが見せる行動の変化に注意
- テレビの音を大きくする
- 呼びかけに反応しにくい
- 学習面での集中力低下
- 頻繁に耳を触る
滲出性中耳炎の診断方法
耳鼻科では、以下の方法で診断を行います。
- 鼓膜の観察:鼓膜の色や凹みをチェック
- ティンパノメトリー:鼓膜の動き具合を測定
- 聴力検査:聞こえの程度を評価
滲出性中耳炎の治療法
経過観察
多くの場合、風邪が治ると自然に滲出液が吸収されるため、すぐに治療せずに経過を観察することがあります。
薬物療法
- 抗ヒスタミン薬・抗アレルギー薬
- 粘液溶解薬
- アレルギー性鼻炎の治療薬
耳管通気
耳鼻科で行う処置で、鼻から耳管に空気を送り、中耳の換気を促します。
鼓膜チューブ留置術とは?
以下のようなケースで行われます
- 3ヶ月以上の滲出持続
- 反復する中耳炎
- 両側40dB以上の難聴
- 鼓膜に病的変化がある場合
小さなチューブを鼓膜に挿入し、中耳内の液体排出を促進します。
局所または全身麻酔で行う安全な処置で、チューブは通常半年~1年で自然に排出されます。
予防方法と家庭での注意点
- 手洗い・うがい・マスクで風邪予防
- アレルギー性鼻炎の適切な治療
- 鼻を強くかまないように指導
- 難聴が続くときは耳鼻科を早めに受診
よくある質問(Q&A)
Q. お風呂やプールは避けた方が良いですか?
基本的にお風呂は問題ありませんが、鼻水が多いときは注意を。プールについては主治医にご相談ください。
Q. 子どもが耳をよく触りますが、滲出性中耳炎の可能性は?
痛みは少ないですが、耳が詰まる感覚などから無意識に触ることがあります。他の症状とあわせて注意が必要です。
Q. 集団保育だと滲出性中耳炎になりやすいですか?
集団生活で風邪をひきやすくなり、耳管の炎症をきっかけに発症しやすくなります。
Q. 何歳頃の子どもに多いですか?
2~7歳の幼児期が最も多く、耳管が未発達なことが関係しています。
Q. 鼓膜チューブ挿入後の聞こえは?
滲出液が排出されることで聞こえが改善されることが多く、聴力に悪影響はありません。
まとめ
滲出性中耳炎は痛みが少なく、特に子どもでは気づかれにくい病気ですが、放置すると学習や発達に影響を及ぼす可能性があります。
テレビの音量や反応の変化など、日常の中で気になるサインがあれば、早めに耳鼻科を受診しましょう。
参考文献
- 日本耳鼻咽喉科学会「滲出性中耳炎診療ガイドライン」
- Otitis Media with Effusion in Children. American Academy of Otolaryngology-Head and Neck Surgery Foundation.
- Rosenfeld RM, Shin JJ, Schwartz SR, et al. Clinical Practice Guideline: Otitis Media with Effusion (Update). Otolaryngol Head Neck Surg. 2016.